メニュー
2022/11/25
美術Ⅰ『文化財を知り、考える~インクルーシブ社会と文化財の活用~』(全5回)では、11月11日と12日に、滋賀県湖南市にある長寿寺と甲賀市にある大塚オーミ陶業株式会社のご協力で、3回目の授業を行いました。
長寿寺の蔵に長い間眠っていた『地蔵曼荼羅』は室町時代に作られました。約12000体のお地蔵様が描かれた大変珍しいものですが、かなり傷んでいたそうです。藤支良道住職はクラウドファンディングを通して費用を集め、大津市にある藤本松雲堂の、手間を惜しまない卓越した伝統技法で、見事に修復されました。さらに、大塚オーミ陶業株式会社により、陶板の表面に曼荼羅の絵柄の線を盛り上げた原寸大の複製品である‘触れる’地蔵曼荼羅が制作されました。最先端技術とそこに携わる技術者のこだわり、『セラミックアーカイブ』という文化財の記録保存の取組みがありました。藤支住職の「お体や目の不自由な方も含め、多くの人に伝えたい」という想いが起点となり、アートとテクノロジーと人々の想いが集まりました。

授業は、黒い布に覆われた‘何か’に生徒が触れることから始まりました。見えない中で触るだけで何がどれほど分かるのかを体験しました。そして、黒い布を外し、そこにあったA4サイズほどの陶板地蔵曼荼羅の試作品を見たあと、お寺から持って来て頂いた実物の地蔵曼荼羅を鑑賞しました。藤支住職は、お寺に陶板による複製品を置いているだけでは通りすぎる人もいる、複製品と参拝者の間で自分が説明すると伝わる…、高齢で目が不自由な方が住職のお話を聞いて、この陶板サンプルを抱きしめられたことなどを話されました。
文化財の現状や可能性、関わる人それぞれの想いを知り、これからのインクルーシブ社会の在り方を考える機会にもなりました。
【生徒の感想より】
・文化財は保存されるだけでなく、活用されないと「生かされない」と分かった。
・普段は当たり前のように物を見ているので、今日の授業では、目が見えない人にとってのアートとは何かについて考えさせられた。せっかく素晴らしい文化財がこんなに日本にあるのだから、それをみんなが楽しむにはどうすればいいか、考えていきたい。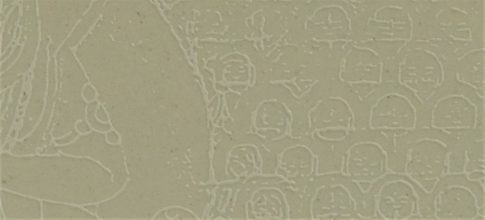
・文化財にはたくさんの人が情熱とプロ意識をもって関わっているんだなということが分かりました。印象に残ったのは絵を修理された職人さんの話でした。三百年後の職人にも恥じない仕事をした、と自信を持って話されたと住職さんから聞いて感動しました。また、大塚オーミさんの重要な文化資源を未来へつないでいきたいという思いで妥協なしで絵の陶板をつくられたというお話を聞いて職人さんのこだわり、プロ意識が感じられました。こういったお話を聞いて企業や職人さんばかりに任せるのではなく、文化財というものはみんなで守っていかないといけないものだなと学びました。
・始めは地蔵曼荼羅を見て「なんだこれ」としか思わなかったが、文化財の発見や修復そして活用の方法を聞き、とても興味がわいた。やはり、それまでの歴史や経緯を知ることで文化財は面白くなると思った。
・文化財を伝える人を、見える人、聞こえる人だけ、自分の近くにいるような人だけに限定していた、と気づき、はっとさせられた。 セラミックアーカイブで未来に、正確な形で残すことができることを知って、展示を見た人に、文化財が消えつつあることについて考えてもらうきっかけになりそうだと考えた。
・私は文化財が見ることが出来るのは当たり前のように感じていましたが、視覚障害のある方は見ることが出来ないということに焦点を当てたことがなかったので、とても印象深い授業でした。また、視覚によって受け取る情報が全てではないということも学びました。触れてみて始めて感じるものもあるという事がわかりました。